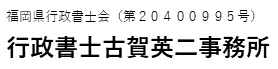遺言

遺言とは、あなたに万一のことがあったとき、大切な人を守るための備えであり、保険と同じようなものです。遺言はあなたの意思を明確に示すものであり、残されたご家族の「相続」が「争族」にならないよう、元気な時に遺言をしておくことは大切なことです。
平成30年のデータで、遺産分割で合意できず、家庭裁判所の調停や審判に持ち込まれた件数は、15,706件になります。およそ1日に43件のペースで家庭裁判所に持ち込まれています。
また、遺産でもめるのは、よほどの財産があるのだろうと思われるかもしれませんが、1,000万円以下が33%、5,000万円以下が43%と、億単位のお金で争っているわけではありません。
ご本人のご家族への思いをかなえ、残されたご家族が困らないように、生前の準備が大切です。
遺言には法的に備えなければならない要件や手続きがありますので、以下に簡単にご説明させていただきます。
遺言の種類
遺言には「自筆証書遺言」・「公正証書遺言」・「秘密証書遺言」の3種類があります。
通常は「自筆証書遺言」・「公正証書遺言」の2種類が主に使われますので、この2種類についてご説明します。
弊事務所では、遺言の改変・紛失がなく、存在が明らかになる「公正証書遺言」をお勧めします。令和2年7月10日より、自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる制度が始まりましたが、これにより自筆証書遺言のデメリットがかなりの部分なくなるため、自筆証書遺言の法務局保管もお勧めです。
自筆証書遺言 (民法968条)
自筆証書遺言は、遺言者が遺言の全文を自書しなければなりません。本文はパソコン等で作成し、プリントアウトしたものは無効となります。財産目録はパソコン作成でも自書の署名押印があれば認められます。また、他人が書いたものや、遺言者が話した内容を他人に書き取らせた場合なども無効となります。遺言書は撤回したり、内容を変更したりすることもできます。遺言書が2通存在した場合は、日付が後の新しい遺言が有効となります。そのため、令和2年4月5日といったように、日付は明確に記入しなければなりません。4月吉日といった場合は無効となります。
作成上の注意点
- 遺言者の自筆であること(添付目録を除く)
- 日付が明確に記入されていること
- 押印がされていること
自筆証書遺言のメリット
- 最も簡易な方法であること
- 費用がかからないこと
自筆証書遺言のデメリット
- 紛失・改変しやすい、いざという時に遺言書の存在を誰も知らなかった等の事がありうる(法務局保管により解決)
- 開封時に家庭裁判所の検認手続きが必要(法務局保管の場合不要)
公正証書遺言 (民法969条)
公正証書遺言は、遺言者が公証役場の公証人に遺言の内容を話して聞かせ、それを公証人が文章にしたものを遺言者に聞かせ、間違いがないか確認したものを公証人が保管する制度です。なお、作成時に2名の証人が必要になりますが、親族は証人になれません。
令和7年10月1日から公正証書の作成手順がデジタル化されました。
作成上の注意点
- 証人2人の立ち合いがあること
- 遺言者が遺言の内容を公証人に口頭で話して聞かせること
- 公証人が遺言書の内容を遺言者及び証人に読み聞かせ、内容を確認し、各自電子サインすること
公正証書遺言のメリット
- 遺言内容が公証役場の原簿に記入されるので、遺言の存在・内容が明確
- 遺言書は公証役場に保管されるので、紛失・改変の恐れがない
- 公証人が確認しているので、法的不備がない
公正証書遺言のデメリット
- 手続きが煩雑
- 公証役場の手数料がかかる
- 公証人・証人が遺言の内容を知るため、秘密が保てない可能性がある
公正証書遺言の公証人に支払う手数料
*注1
財産の相続又は遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出し、これを上記基準表に当てはめて、その価額に対する手数料額を求め、これらの手数料額を合算して、当該遺言書全体の手数料を算出します。
*注2
遺言加算といって、全体の財産が1億円以下のときは、上記注1によって算出された手数料額に、11,000円が加算されます。
遺言書作成の流れ
遺言書を作成するためには、決められた法律の要件を満たす必要があります。そのための必要なアドバイス・お手続きをさせていただきます。
- お電話もしくはメールでのお問い合わせ
- 遺言内容のヒアリング
- お見積もりの提示後、正式な契約、実費がかかる場合はその分のお支払い
- 遺言書原案作成
- 遺言書作成
- 報酬のお支払い
ヒアリングさせていただいた内容を基に、遺言書の原案を作成します。原案は弊事務所にて作成しますので、文章作成に不安がある方もご安心下さい。内容にご納得がいくまで、原案は何度でも作り直します。
(A)自筆証書遺言の場合
原案を見ながら、遺言者自身が自書します。記入・捺印後、チェックの上封かんし、保管します。
(B)公正証書遺言の場合
原案を公証役場に提出します。後日遺言者と証人2名で公証役場に出向き、公正証書遺言の内容を確認します。行政書士も同行しますので、ご安心下さい。
遺言に関するQ&A
遺言は夫婦で一緒にできるの?
遺言は1人でしかできません。ご夫婦で遺言をする場合は、それぞれで遺言書を作成することになります。
遺言書の内容は変えられるの?
遺言の内容は何度でも変えられますし、なかったことにもできます。
遺言書が2通出てきた時はどうなるの?
日付の新しいものが有効になります。遺言書が新しく変更されたとみなされます。
遺言書は必ず書かれた通りに実行されるの?
遺産分割協議で相続人全員の同意があれば、遺言書と違う分割をすることは可能です。また、相続人には遺留分侵害額の請求が認められています。この遺留分侵害額の請求が行われた場合、遺言の内容が修正されることがあります。
*遺産分割協議とは、相続人全員で分割の話し合いをすることです。
*遺留分侵害額の請求については、相続の項目をご覧下さい。